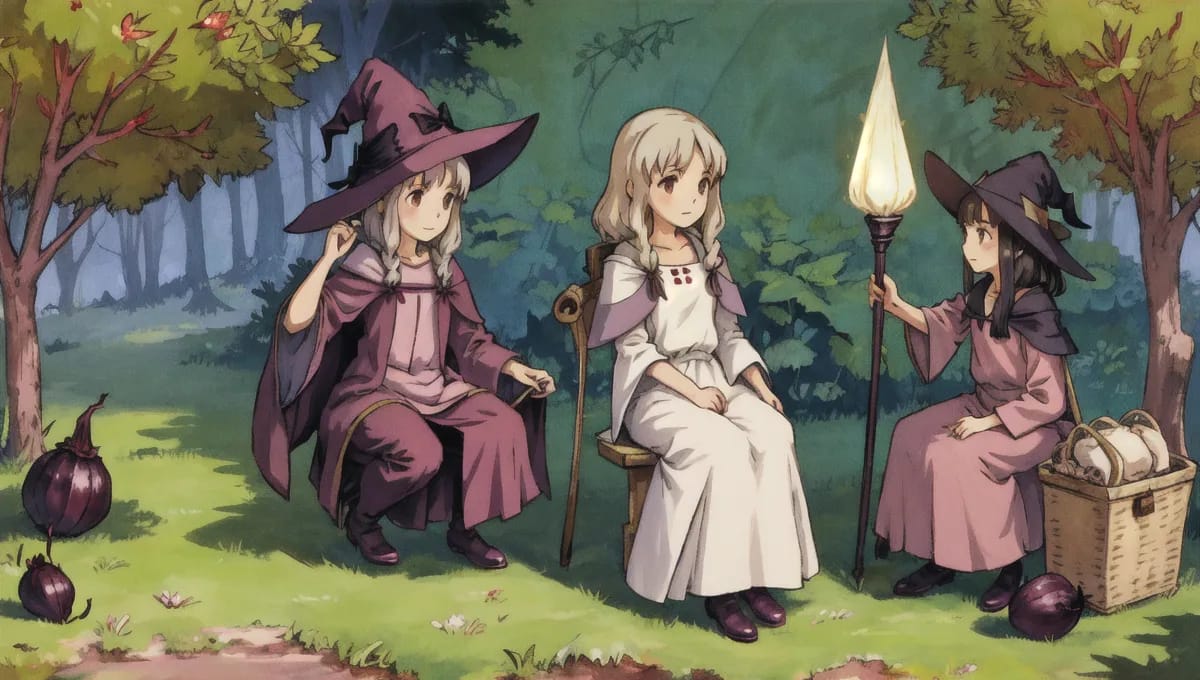睡眠時間と脳の関係
「昨日憶えたと思っていたのに、いつの間にかきれいさっぱり忘れていた」。そんな経験、誰しも一度はあるのではないでしょうか。覚えることも忘れることも人生にはつきものです。本屋やネットでは「記憶力を高める○○法」があふれ、「脳トレ」や「記憶食事法」まで登場。ですが、多くの人がつい見落としてしまうのが、睡眠と記憶力の関係です。
実は、眠っている間に人間の脳は「記憶の片付け屋」へ早変わりします。一日の間に溜まった膨大な情報の中から、いらない情報はほどよく掃除され、大切な情報はしっかりと引き出しにしまわれて整理されています。この作業のおかげで、私たちは翌日また新しい情報を効率的に処理することができるようになります。まるで夜中にこっそり引越し作業をして、新しい生活の準備を整えてくれる頼れる存在のようです。睡眠の質が記憶や学習能力に影響を与えるのも、このプロセスが関係しているのだそうです。
今回の記事では、「記憶力」「睡眠」「記憶と睡眠」「記憶力を高める」など、実生活で役立つ視点から、「睡眠」を味方につけるヒントを探ります。読み進めるうちに、「ちょっと枕の存在、見直してみようかな」なんて思っていただければ嬉しいです。睡眠不足の人はもちろん、夜型生活の人にも少し役立つ情報をお届けしたいと思っています。
記憶のメカニズムと脳内で起きていること
「昨日話したはずなのに、もう忘れてしまった?」という経験、一度はありませんか。メモを見返しながら、先週のランチの内容すらふんわりしか思い出せない自分に苦笑してしまいます。でも、これは決して「記憶力が悪い」だけが原因ではありません。実は、私たちの脳はとても複雑で繊細なメカニズムを持っており、記憶もその一つに含まれるそうです。
まず、「記憶力を高める」ために知っておきたいのは、記憶がどのように整理されているかという点。記憶はざっくりと「短期記憶」と「長期記憶」に分かれます。短期記憶は、頭に入ってきた情報を一時的に保管する場所。コンビニのおつりや、メールの件名、数秒ですぐ消えてしまう“付箋割をしています。一方で長期記憶は、テストの英単語や大切な約束ごとなど、何度も呼び出すことで脳が、「これは大事だ」と判断した情報が、しっかりファイルされるイメージです。
では、なぜ「暗記モノが苦手」と感じるのでしょうか。その理由のひとつは、情報がうまく「長期記憶の棚」にしまわれなかった、もしくは出し入れがうまくいかなかったケースが多いからかもしれません。特にストレスや睡眠不足の日は、昨日の晩ご飯さえまるごと記憶から消えてしまうこともあるそうです。
もうひとつ、記憶が定着するかどうかに大きく関わっているのが、海馬(かいば)という脳の部位。海馬は、まるで図書館の司書のように情報を一時保管し、「これは必要か?いらないか?」と仕分け作業をしてくれます。そして、本当に必要な情報だけを大脳皮質へと運んでくれるのです。つまり、記憶力アップの“陰のヒーロー”ともいえる存在。
科学的に見ても、記憶には入力(エンコーディング)、保存(ストレージ)、呼び出し(リトリーバル)という3ステップがあります。覚える作業も、この3つをうまく経ることで記憶が自分のものになるのです。逆に、たとえ一度覚えても、保存や呼び出しのどこかでミスが起これば「あれ、思い出せない」という現象が起こります。
結論として、「記憶力を高める」ためには脳の仕組みを知り、脳の付箋からしっかりしたファイルへと情報を移動させる意識が大切。今、この記事を読んでいるあなたの脳も、着実に新しい知識をファイリングし始めているはずです。
結論として、「記憶力を高める」ためには脳の仕組みを知り、脳の付箋のような一時的な記憶から、しっかりとしたファイルのような長期記憶へと情報を移動させる意識が大切です。そのためには情報を繰り返し復習したり、関連性を見つけて深く理解すること、さらに五感を活用して記憶を定着させることが効果的になるそうです。
例えば、学んだ内容を人に教えることや、具体的なイメージやストーリーに結びつけることで、記憶に残りやすくなります。今、この記事を読んでいるあなたの脳も、きっと新しい知識をファイリングし始めていることでしょう。この記憶の習慣を続けることで、記憶力を向上させる可能性が高まるそうです。
睡眠が脳にもたらすもの
「睡眠」と聞いて思い浮かべるのは、目を閉じて体を休める姿かもしれませんが、脳の中では複数のスタッフが順番に活躍しています。レム睡眠とノンレム睡眠。このふたつがペースを作り、記憶力を高めるための裏方として欠かせない存在となっています。
レム睡眠は「夢を見る時間」として知られていますが、実は記憶の再構築という大仕事をこなしている時間帯でもあります。一方、ノンレム睡眠は、日中に得た情報を“整理整頓”する脳のメンテナンスタイム。引っ越し作業に似ています。日中詰め込んだ情報や体験というダンボール箱たちが、まずノンレム睡眠で開けられ、「これは残す、これは処分」と選別されます。大事な記憶は長期記憶の倉庫へ運ばれ、不要な情報は思い切りよく消去されていくのです。
こうして脳内の片づけが進むことで、例えば昨日のランチの味はちゃんと記憶として残り、店内の雑音やBGMのような細かい情報は忘れやすくなります。レム睡眠では、このように整理した情報同士が結びつき、新しいひらめきや問題解決力にも貢献するようです。寝て起きたら難題がスッキリ解決、という体験も、この夜の引っ越し&リフォームの成果かもしれません。
「睡眠=何もしていない時間」というイメージは誤解かもしれません。脳内では複数の作業スタッフがバトンをつなぎ、記憶の管理に取り組んでいます。朝起きて「頭がスッキリした」と感じるのは、余計なメモやファイルがすっかり掃除されたから。「朝イチの脳は新品同様」と感じるのも、このおかげかもしれません。
忙しい毎日のなかでも、脳の夜勤スタッフはせっせと働いています。記憶力を鍛えたいときは、短時間でも質の良い深い睡眠を意識してみるのもひとつの方法だと思います。
十分な睡眠が記憶に与えるポジティブな効果
記憶力と睡眠の関係と聞くと、「ああ、よく寝たほうがいいんだよね?」となんとなく想像する方が多いかもしれません。でも、その「なんとなく」の背景には、科学的な裏付けがしっかりあるのをご存じでしょうか?
たとえば、ハーバード大学やペンシルベニア大学の研究では睡眠が少なければ少ないほど、彼らのスコアは悪くなります。また、深い睡眠は、記憶保持を20~40%改善する可能性が明らかになっています。
睡眠研究によると、一晩しっかり睡眠をとった人の方が、日中に新しく覚えた内容を翌日もしっかり思い出せる傾向があると指摘されています。逆に寝不足が続くと、脳内の記憶定着ネットワーク(海馬など)がうまく働かず、「昨日やったはずなのに内容が抜け落ちている」といった「ど忘れ」が起こりやすいそうです。
女性の社会人に多い「寝不足+仕事+家事」を抱えたとき、「何を買うつもりだったかスーパーに着いたら忘れていた」という残念なエピソード、思い当たりませんか?私自身も寝不足の日ほど、「昨日思い浮かんだ執筆のアイデアがどうにも思い出せない」という経験が何度もあります。これは一種の脳の「省エネモード」なのかもしれません。
では、どのくらい寝れば記憶力が高まるかというと、これは体質や年代にもよるため一概には言えません。ただし、「自分が心地よく目覚められる睡眠時間を毎日確保する」ことが、脳のパフォーマンス維持に役立つというのが最近の定説です。寝不足気味の方は、先週と今週で記憶力の持続や“ど忘れ率”を比べてみるのも一つの方法。寝た分だけ頭がすっきりするか、自分なりのデータを小さく取ってみるのも面白いかもしれません。
寝不足、と一口にいっても原因はいろいろです。スマホの深夜スクロール、限界まで残業、徹夜でネットゲーム。どれも身近なことですが、実は「寝てない=物忘れが増える」の図式にピタリとハマります。研究データを確認すると、「寝不足の日ほど名前や約束事をうっかり忘れる頻度が高くなる」傾向がはっきり出ているそうです。
「今日は絶対に忘れ物しないぞ」と気を引き締めた日に限って、そもそも何を忘れたか思い出せない。そんなコミカルな失敗談が取引先の社長からもありました。仕事がうまくいかない日に限って、原稿やプレゼンテーション資料の“あれ?どこいった??”が増える、という話もよく聞きます。
科学的なエビデンスだけでなく、身近な経験談もあわせて振り返ると、「記憶力」と「睡眠」は切っても切れない関係にあります。寝不足でも頑張らなきゃいけない日も多いかもしれませんが、少しの睡眠の質・量アップが、記憶対策に効果的かもしれません。まずは今日から「ちょっとだけ早く寝てみる」ことが、意外な第一歩になると思います。
睡眠不足がもたらす記憶への悪影響
記憶力を高めるために睡眠が必要になる。と少し理解できたように思いますが、正直なところ「睡眠不足でどれだけ困るの?」と思ったことありませんか。私自身、集中的な仕事の追い込みや、気になるドラマをずっと見続けってしまい、寝不足になった朝に「昨日の会話内容がぜんぜん思い出せない」「通勤バッグに入れたはずの鍵をなくす」など、まるで「脳の迷子」状態に。心当たりがある人もいるかもしれません。
そもそも、睡眠不足が脳に与える影響は意外と侮れません。脳科学の観点から見ると、睡眠不足になると「海馬(かいば)」と呼ばれる記憶の司令塔の働きが鈍くなり、新しい情報が入りづらくなります。具体的には、前日に起こった出来事や学んだ知識がしっかり“保管庫”に運ばれず、短期記憶のまま消えていくそうです。
「まあ、そのうち思い出すでしょう」と楽観視していると、いつの間にか大事なタスクや約束までポロリと抜け落ちてしまうことも。個人的な体験では、寝不足だった日にはいつのまにかスマホが消えていたり、知人の名前がどうしても出てこなかったり、ちょっと笑えない失敗もあります。振り返ると睡眠が記憶の定着に欠かせない作業であることを身をもって痛感しています。
慢性的な睡眠不足は「注意力散漫」や「判断力の低下」も同時に招きます。「自分だけは大丈夫」と思っている人こそ要注意です。なぜなら、睡眠不足になるほど「ど忘れ」や「物忘れ」の頻度が明らかに増えるという調査データも複数存在します。仕事と家事に忙しい女性や責任を持つ仕事で忙しい男性ほど、「寝ている場合じゃない」と夜更かししがちですが、翌日のパフォーマンスを考えると一度立ち止まって布団に入るほうが賢明かもしれません。
まとめると、睡眠不足は記憶力にちょっとした“意地悪”をしてくる存在です。「昨日の晩ごはん、何食べたっけ?」と戸惑う回数が増えたら、脳からのSOSサインかも。たまにはちょっぴり早めに布団に入り枕に頭をのせて「あぁ、これで記憶力も回復するかも」と、心の中でつぶやいてみてください。朝起きた時、きっと頭の回転が違うはずです。